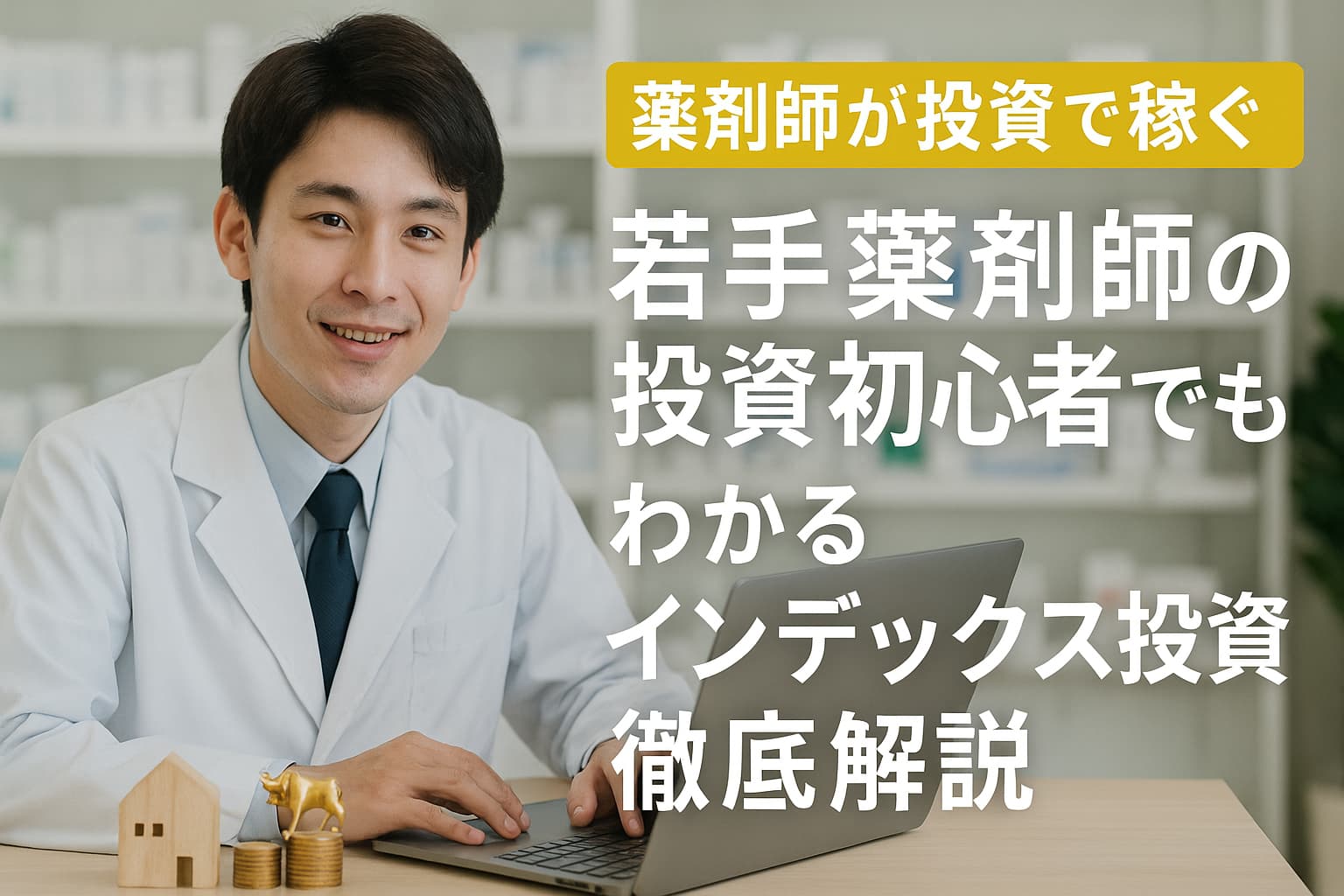お金の制度を知りたい薬剤師必見!NISAとiDeCoの違いを徹底解説【初心者向け】

投資を始めようとすると必ず聞く「NISA(ニーサ)」と「iDeCo(イデコ)」。
最近お金の制度に興味を持ち始めた薬剤師さんの中には、「NISA」と「iDeCo」という言葉は聞いたことがあっても、それぞれ何ができてどう違うのかピンと来ない方も多いでしょう。
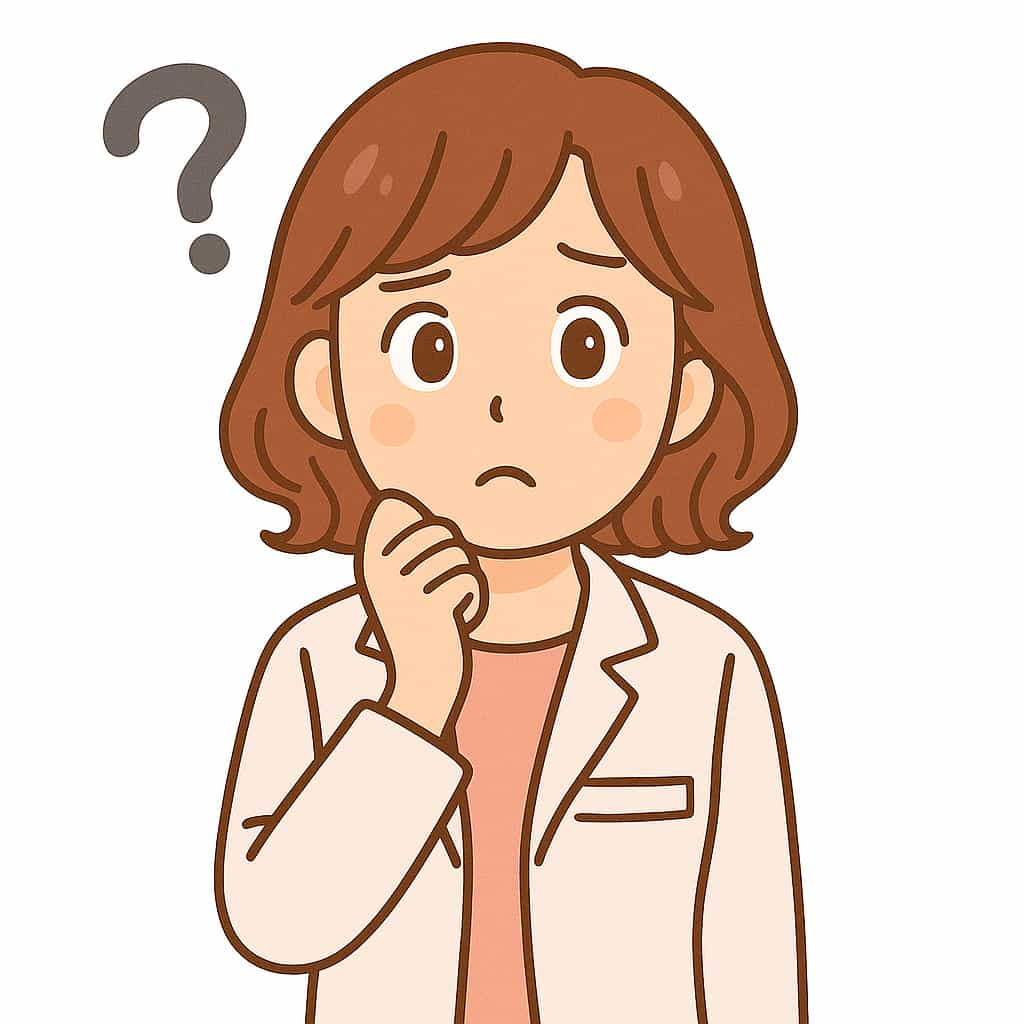
ニーサもイデコも聞いたことあるけど結局何なの?
そこでこの記事では、現役薬剤師でファイナンシャルプランナーでもある筆者が、「NISA」と「iDeCo」の違いを説明し、どのような人、場合にオススメなのかを分かりやすく解説します。
この記事を読めば「NISA」と「iDeCo」を理解し、より効率的に目的に沿った資産形成を行うことができます。
実際に筆者が「NISA」「iDeCo」を行う上で考えた目的や資産配分の経験をまとめました。
「NISA」「iDeCo」をうまく活用したい薬剤師は、ぜひ最後までお読みください。
結論:NISA、iDeCo両方行うことが理想だけど、若い人はNISAから行うとよい
どちらも投資の利益に税金がかからないというお得な制度ですが、その仕組みや使いどころには大きな違いがあります。
結論から申し上げますと
NISA→住宅資金や教育資金など明確に目的の定まっていない資金向け
iDeCo→老後資金を形成する資金向け
になります。
NISAは若手の薬剤師のうちから、iDeCoは人生設計が決まったタイミング(中堅薬剤師など)がおすすめです。
併用できるので両方早くから行うことが理想ではありますが、制度も目的も異なるので個人に合わせて上手に使っていくことも重要です。
ではそれぞれの特徴を見ていきましょう。
NISA(ニーサ)とは?少額投資非課税制度の基本(新NISA対応)
まずはNISAから解説していきます。
NISA(Nippon Individual Savings Account)とは「少額投資非課税制度」といって、株式や投資信託などに投資して得られた売却益や配当金(株式の場合受け取り方に制限あり)が非課税になるお得な投資制度です。
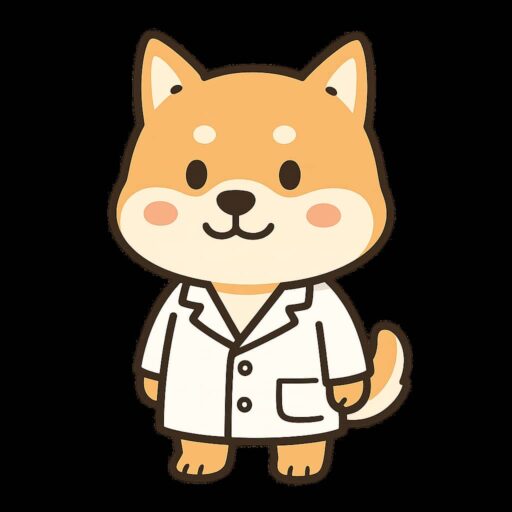
イギリスの「ISA(アイサ)」をモデルにして導入されました!
通常、日本では株や投資信託の利益に約20%の税金がかかりますが、NISA口座で運用すればその税金がかからないため、利益をまるごと手元に残せます。
2024年からNISA制度が「新NISA」に刷新され、より使いやすくなりました。新NISAでは非課税で運用できる期間が無期限となり、制度自体が恒久化されています。
これにより「何年までに使い切らないといけない」といった心配をせずに長期投資が可能です。
また、年間の投資枠は最大360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)に拡大し、生涯の非課税保有枠も1,800万円まで大幅アップしました 。
※ 成長投資枠の利用は生涯1,200万円までという内訳があります。

引用元:金融庁ホームページ
NISAは日本に住む18歳以上であれば誰でも利用できます。
NISA口座は証券会社や銀行で開設でき、口座管理料は基本無料です (売買手数料は別途かかる場合あり)。

つみたて投資枠?成長投資枠?なにそれ?
簡単に言うと買える商品と買うときの目的が異なることが大きな違いです。
NISAで運用できる商品は、株式や投資信託など多岐にわたりますが、新NISAでは2つの投資枠があり「つみたて投資枠」では長期積立に適した一定の投資信託のみ、「成長投資枠」では個別株やETF・投資信託(一部リスクの高い商品は除外)など幅広い商品が対象です 。
・つみたて投資枠はコツコツ積立専用
・成長投資枠は一括投資もでき柔軟に運用可能
とイメージするとよいでしょう。
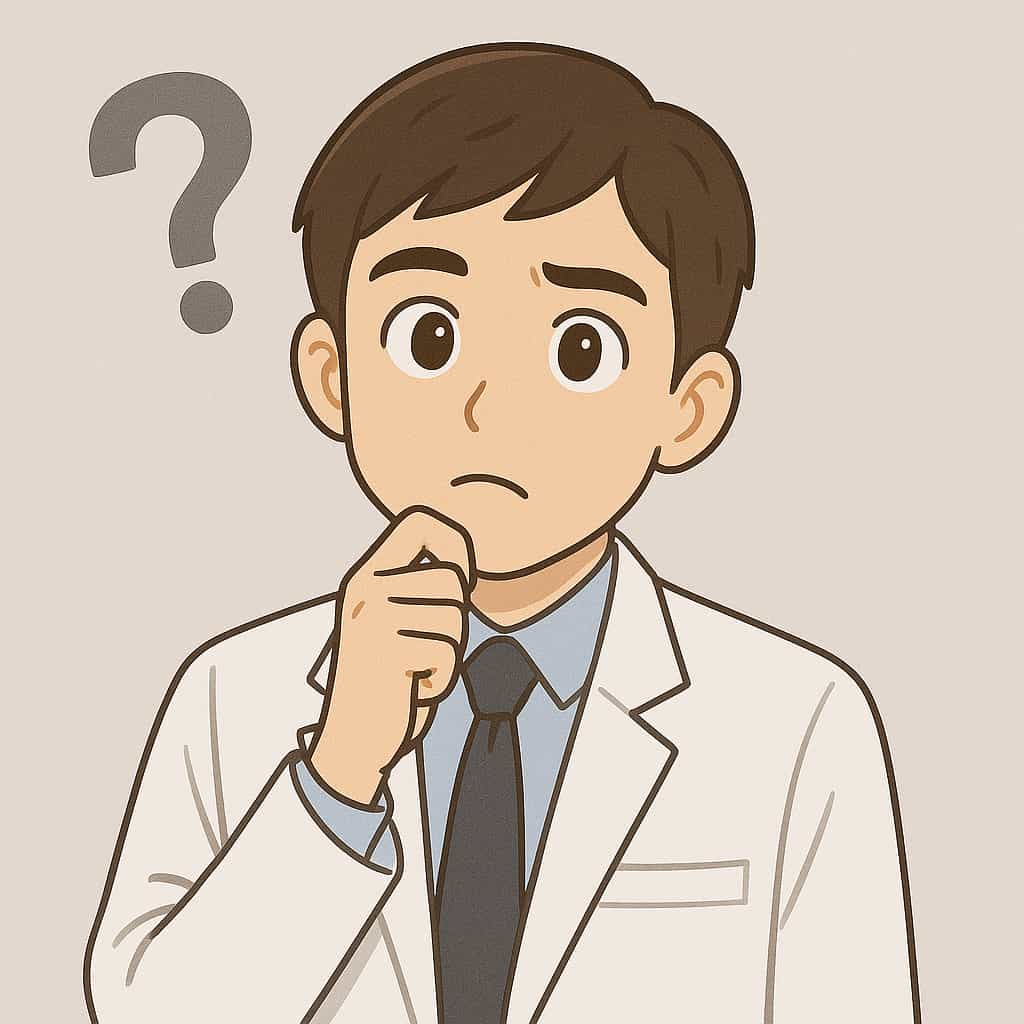
なるほどね。けど、いきなりお金が必要になる時、例えば家や車を買ったりするときにはNISAからお金を下ろせたりするの?下ろせないの?
NISAは資金の出し入れが自由なのも特徴です。いつでも途中で売却して資金を引き出すことができ、使いみちにも制限がありません。
例えばNISAで運用したお金は、教育費や住宅購入費、老後資金など好きなタイミングで好きな用途に使えます。
その分、「つい使ってしまって将来の貯蓄が残らない」といった自己管理の難しさもありますが、必要なときにすぐ引き出せる柔軟性は大きなメリットです。
iDeCoとは?個人型確定拠出年金の基本
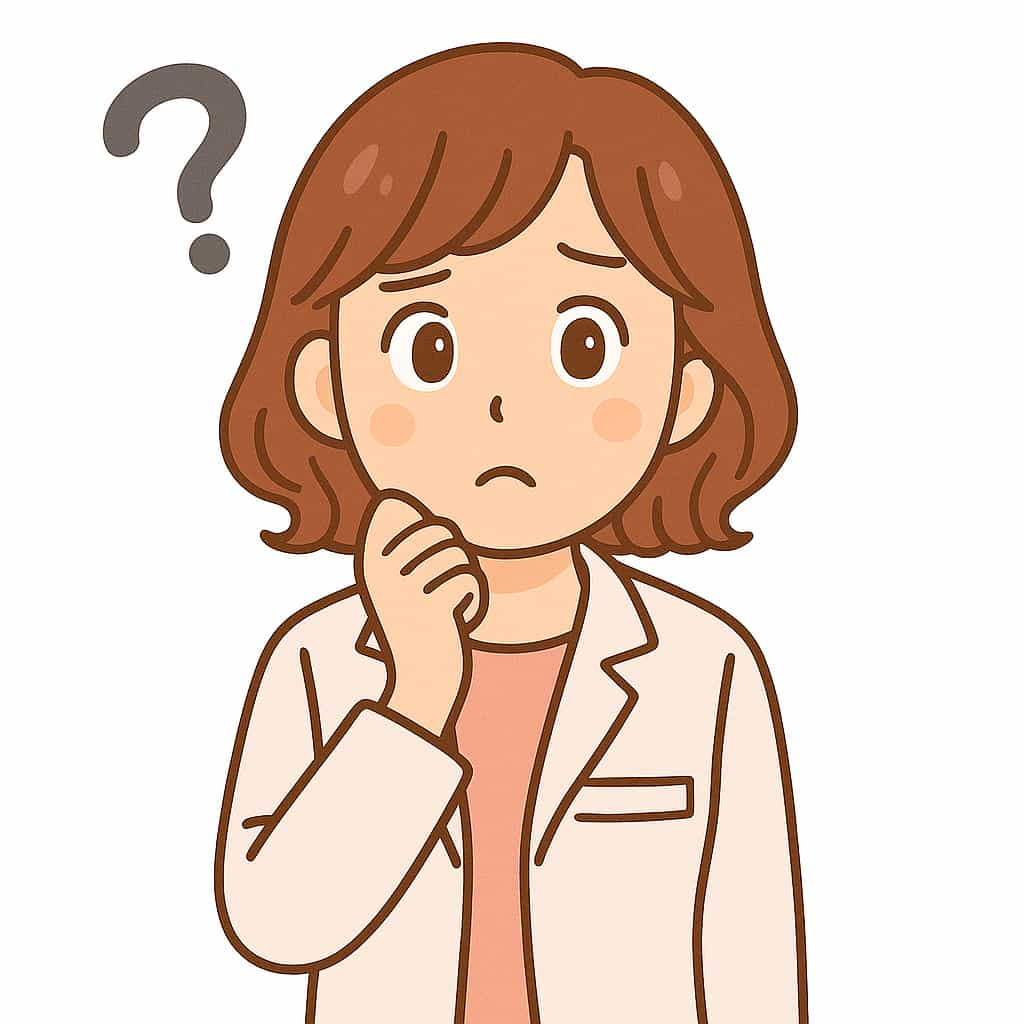
NISAはわかってきたけど、じゃあiDeCoはなに?
iDeCo(individual-type Defined Contribution pension plan)とは「個人型確定拠出年金」の略称で、自分で積み立て運用していく私的年金制度です。
公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せして老後資金を準備するためのしくみで、加入は任意ですが、税制面で非常に優遇されています。
具体的には、iDeCoには次の3つの大きな税制上のメリットがあります 。
①掛金が全額「所得控除」になる
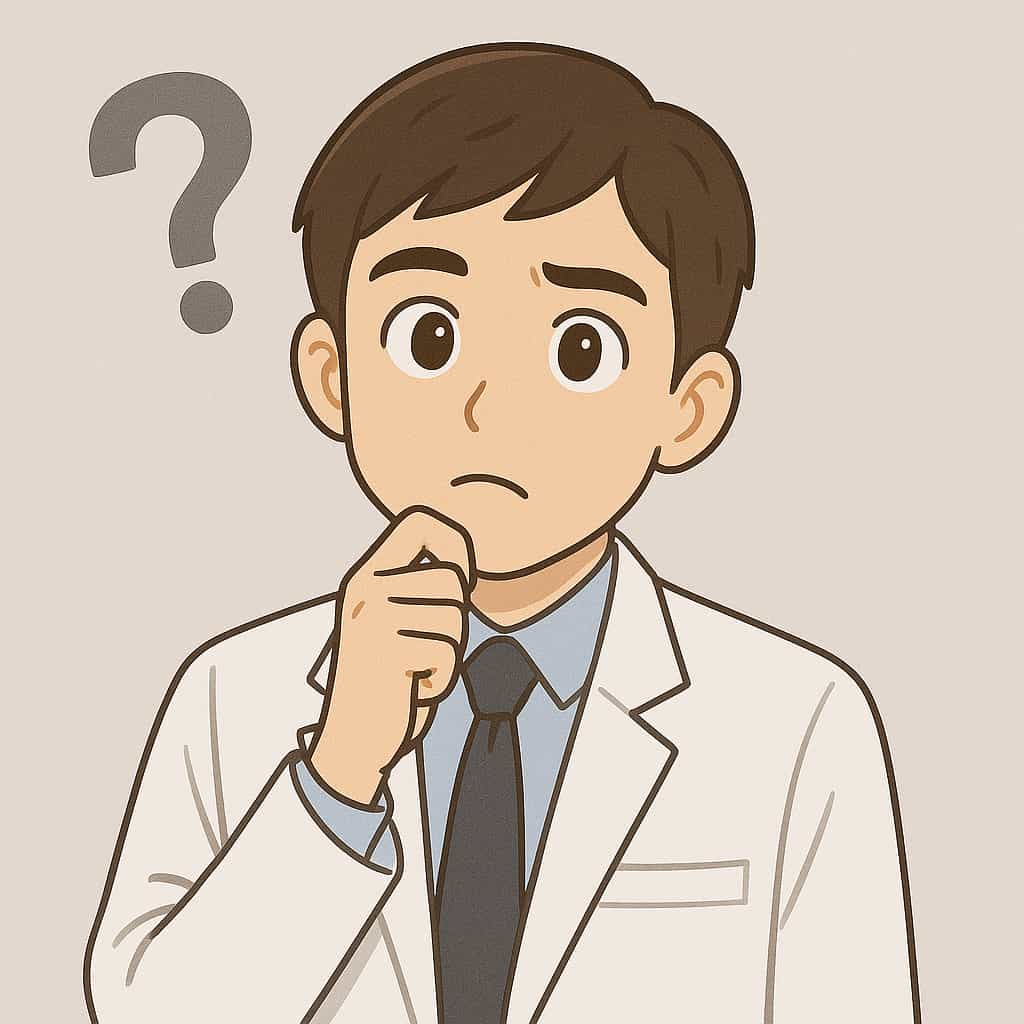
所得控除ってなに?知らない言葉なんだけど、、、
そうですよね。薬学部では全く勉強することのない内容なので簡単に説明します。
所得控除とは「税金を計算するときに、収入から差し引いてもらえる金額」です。
例えば
あなたが薬剤師として働いていて、年収が500万円あるとします。
でも、いきなりこの500万円に税金がかかるわけではありません。
ここで所得控除が120万円あったとすると
500−120=380万円
に対して税金がかかってきます。
実際は様々な控除があるのですが、今回は所得控除のイメージのみに焦点を当てました。
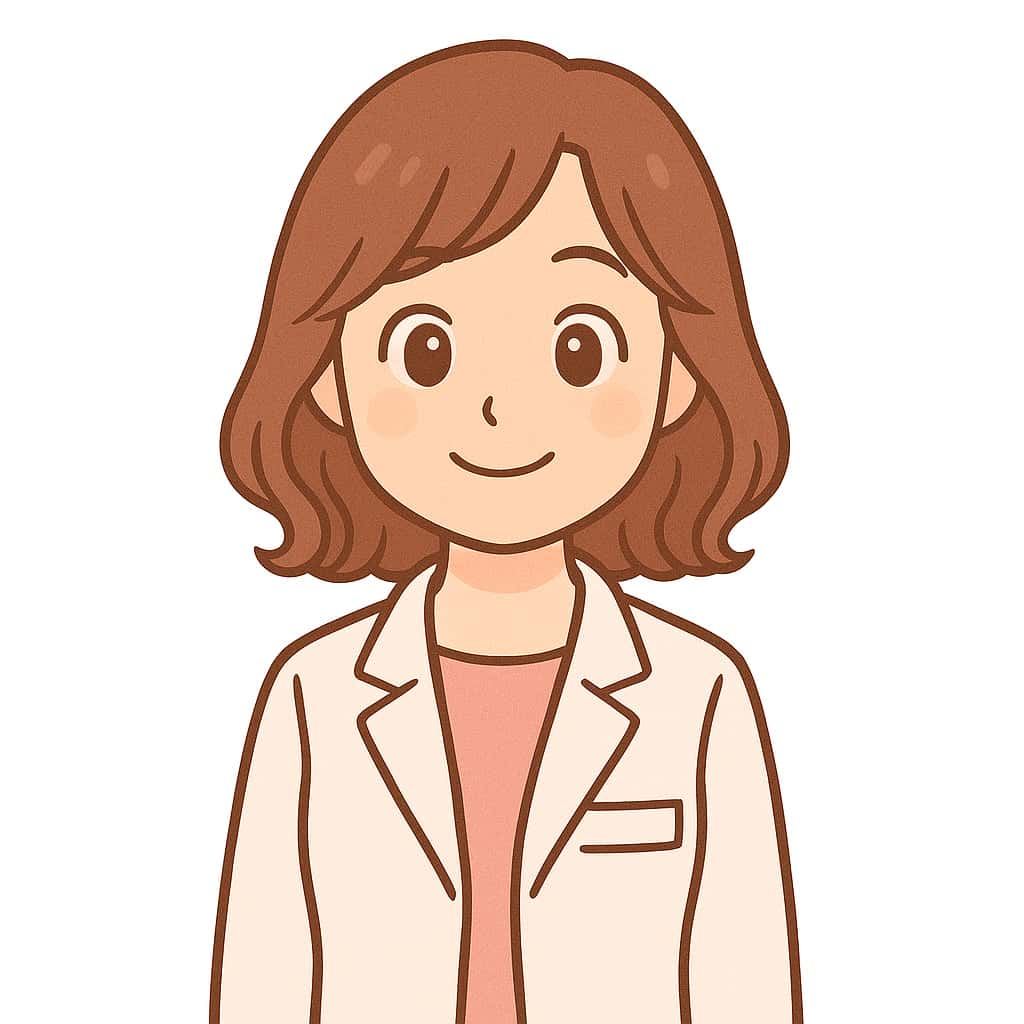
年収全体に税金がかかるわけではないんだね!
そして、iDeCoは毎月拠出する掛金の全額が所得控除の対象となり、その分給与所得などにかかる税金が軽減されます。
簡単に言えば、iDeCoで積み立てた金額はまるまる税金計算から引かれるため、薬剤師のように年収が高い人ほど節税効果が大きくなります。
② 運用益が非課税
NISAと同様、iDeCo口座で運用して得た配当・売却益などの投資収益も非課税になります。長期運用で利益が出ても税金で目減りしません。
③受け取るときも税優遇あり
iDeCoの給付金を60歳以降に受け取る際、一時金で受け取るなら「退職所得控除」、年金形式で受け取るなら「公的年金等控除」が適用され、大部分が非課税または低い税率で受け取れます。
以上がメリットです。
ただし、iDeCoは老後資金づくりに特化した制度ゆえのデメリット(制約)もあります。
iDeCoのデメリットは資金が固定化されること
最大の注意点は、原則60歳になるまで積み立てたお金を引き出せないことです 。
いったんiDeCo口座に入れた資金は60歳 まで“貯金箱”に封印されるイメージで、住宅購入や教育資金などに途中で取り崩すことはできません。
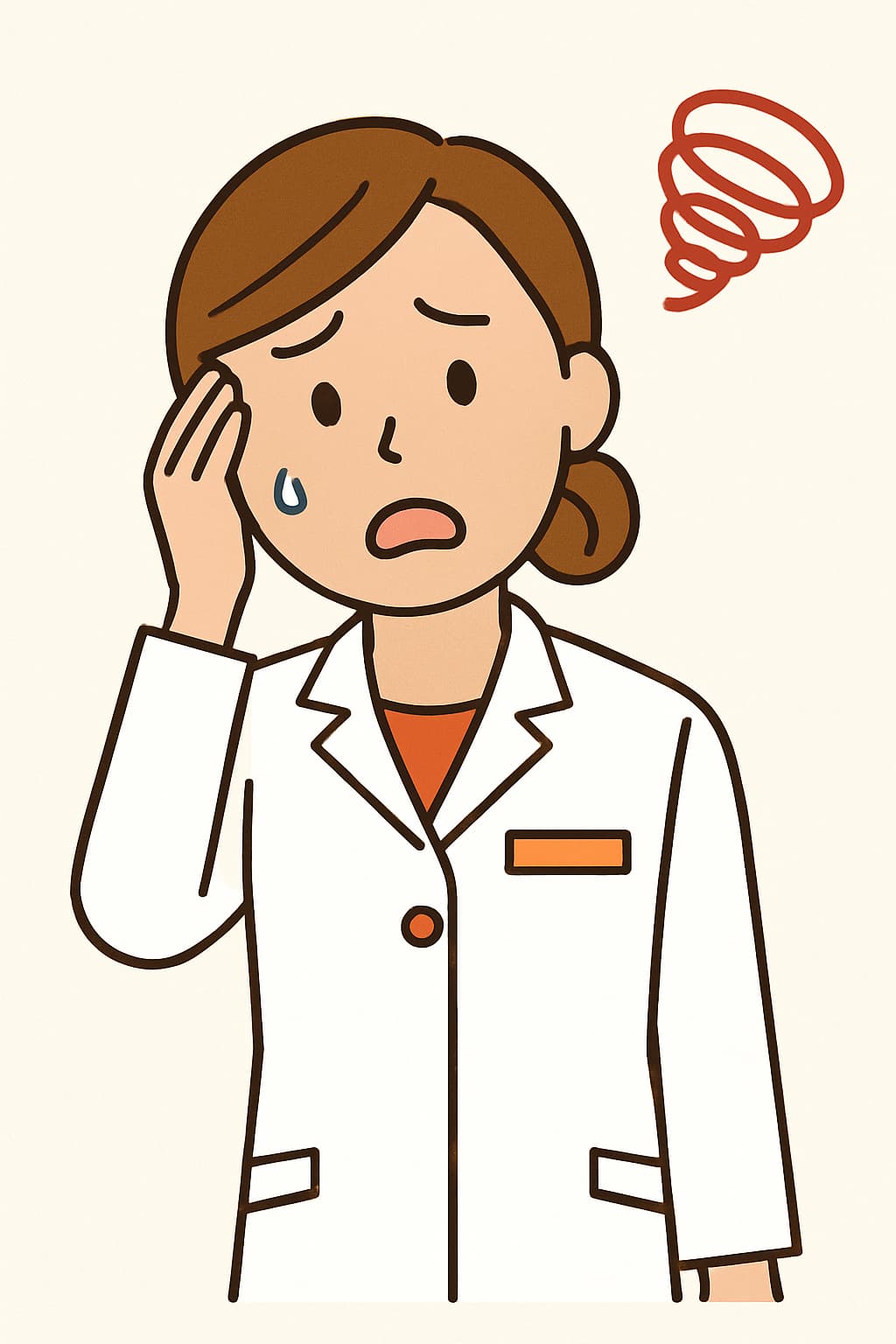
いざ必要なときに切り崩せないのは心配かも?
そうならないようにNISAとiDeCoをうまく使い分ける必要があります。
裏を返せば、「iDeCoは割れない貯金箱」とも言われ、途中で手を付けられない分確実に老後資金を貯められるメリットでもあります。
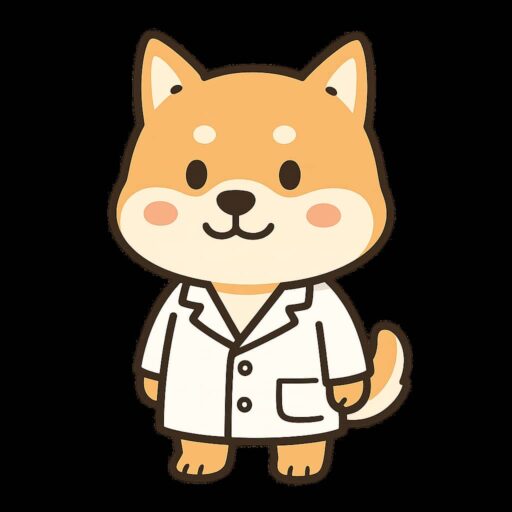
貯金が苦手な人にもいいかもしれませんね。
加入できる人と掛金の上限もiDeCo独自のルールがあります。
加入資格は原則として20歳以上60歳未満の国民年金加入者と扶養されている配偶者です(※条件満たせば65歳未満まで延長加入可能)。職業のタイプによって毎月拠出できる掛金の上限額が異なる点にも注意しましょう。
• 自営業者・フリーランス(国民年金第1号被保険者):月額68,000円
• 会社員(企業年金なし):月額 23,000円
・会社員(企業型DC加入者):月額 20,000円
• 専業主婦(夫):月額 23,000円
このように、自営業など企業年金がない人ほどiDeCoで拠出できる額が大きく、会社員は上限が低めに設定されています。
薬剤師の場合は多くが会社員だと思うので、月2万円前後が掛金の上限となるケースが一般的です。
上限内であれば月額5,000円から1,000円単位で自由に掛金額を設定でき、途中で増減させることも可能です。
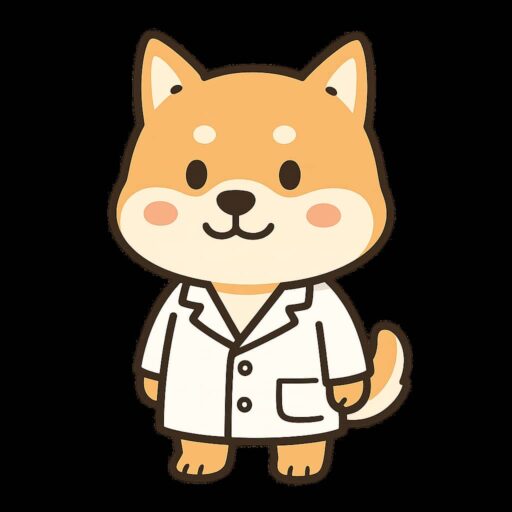
薬剤師は退職金が少ない会社も多いので、老後の対策にはぴったりかもしれません。
なお、iDeCoには口座管理に所定の多少の手数料がかかり、これら手数料は掛金から天引きされます。
一方、 NISA口座は維持手数料が不要なためコスト面ではNISAが有利となります。
運用できる商品にも違いがあり、iDeCoでは多くの場合定期預金・投資信託などから運用商品を選びます。
元本確保型(預金など)も選べるため「投資は怖いから預金でiDeCoの節税だけ活用」 という手も可能です。
ただし元本保証の商品だと運用益は期待できないので、節税メリット+αの運用益を狙うなら信託報酬の安いインデックス型の投資信託などをオススメします。
まとめ:NISAとiDeCoの制度を理解し状況に合わせて使い分け資産形成をしよう
ここまで見てきたNISAとiDeCoの特徴の違いを表にします。

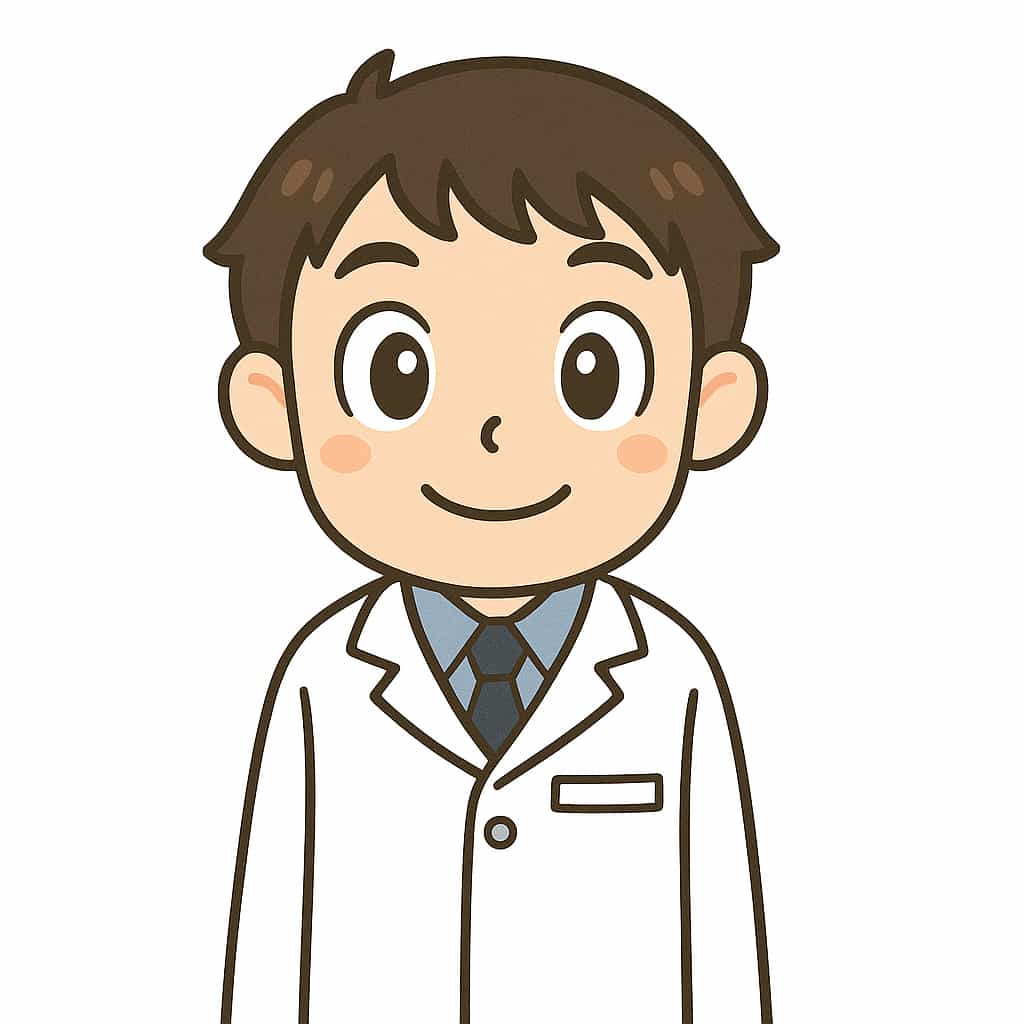
NISAとiDeCoは目的も内容も違うんだね!
もちろんNISAもiDeCoも両方できることが理想ですが、現在の生活をしっかり楽しむことも重要です。余剰資金をうまく利用し効率的に豊かな将来を作っていきましょう!
NISAとiDeCoを始めるにあたっておすすめの証券口座は楽天証券かSBI証券です。
証券口座についてはこちらをご覧ください。

ここまで読んでくださった読者の方々ありがとうございます。
今が一番はじめるには早い日です。いち早く動くことで豊かな未来を掴めるように応援しております。
今後も皆様の役に立てるような情報を発信していきたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。